建築物の移転といえば、プレハブの事務所や倉庫をレッカーなどで動かすことや、(通称)仮設便所を動かすなどが想像されます。
また移転について、平成27年(2015)制度の改正がありました。
そこで、この記事では、
はてな
- 移転とは
- 改正前と改正後の制度の違い
について、解説します。
事例が、まだまだ少ない特定行政庁もあるため、この記事を参考にご確認ください。
移転【法第2条第1項第13号】
既存の建築物を解体することなく、そのまま敷地内および別の敷地に移動させることです。
通称、曳家(ひきや)とも言います。
現在は移転の技術の向上や、移転ありきでの建築をするなど、以前より移転がしやすくなっていると思います
既存の建築物を一旦解体し、移転先で元通りに組み立てることは新築扱いになります。
※プレハブ倉庫などを移動させるのがこれにあたります。
移転とは、法第2条第1項第13号の建築のところに記載されています。
法第2条第1項第13号
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転するこという。
関連
-

建築工事の種類【法第2条第1項第13号】
一般的に家を建てる場合は、家を建築する、建て替える、増築するといわれます。 また、家をきれいにする場合は、改修するやリフォームするといわれるかたが多いです。 そこで、建築基準法では、工事の種類によって ...
続きを見る
-
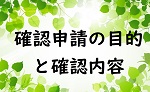
建築確認申請の目的と確認内容とは?【法第6条】
建築物を建築する前には、原則、建築確認申請が必要な工事が法第6条に定められています。 新築はさることながら、防火地域・準防火地域では、1㎡の増築でも確認申請の手続きが必要となります。 そこで、下記の疑 ...
続きを見る
-
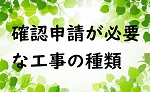
建築確認申請の手続きが必要な工事の種類【法第6条】
建築物の工事をする前に、建築確認申請の手続きが必要です。(法第6条) しかし、建築物の工事の種類といえば、一般的に【新築・増築・リフォーム・改修】などの言い方あります。 よって、小さな増築、リフォーム ...
続きを見る
改正
平成26年法律第54号(平成27年6月1日施行)により、移転の扱いが改正されました。
改正理由の主な理由は、既存ストックの有効活用です。
改正前
改正前の建築基準法では、既存建築物を同一敷地内に曳家(ひきや)で移動する場合のみ、【移転】としていました。
敷地内で移転する場合のみ、既存不適格のまま移転が可能で、別敷地に移動させる場合は、新築として扱われていました。
そのため、別の敷地に移転する場合は、既存不適格を解消をする必要があり、あまりメリットがありませんでした。
改正後
解説
法第3条第3項第3号に移転を加え、移転した場合に現行基準に遡及適用されるように改正されました。
また、法第86条の7第4項が追加し、政令(第137条の16)で定める範囲内で、敷地外への移転も含め既存不適格に対する制限の緩和を行えるように改正されました。
施行令第百三十七条の十六
法第八十六条の七第四項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 移転が同一敷地内におけるものであること。
二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。
特手行政が認めるものとは
特定行政庁が、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと認める基準として、「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」の技術的助言があります。
平成27年5月27日付国住指第558号(国住街第40号)
関係するところだけを抜粋しています。
第6 移転(法第3条及び第86条の7第4項関係)
敷地外への移転の運用に当たり、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上の支障の有無を特定行政庁が判断する場合の考え方について以下のとおり整理したので参考にされたい。
なお、個々の事例ごとに判断すべきものであることに留意されたい。
1.構造、防火・避難、衛生などの単体規定(法第2章)は、建築物の物理的な構造に関する基準であり、当該建築物に対して改修等を実施しなければ現行の建築基準に適合させることはできない。
しかしながら、曳家による移転は、建築物の上部構造には基本的に手を加えない行為であるため、現行の建築基準への適合を求めると、増改築以上に建築主に負担が生じることになると考えられる。
したがって、曳家による移転において、既存建築物の物理的な構造に関する基準は、上部構造だけをみれば移転前よりも悪くならないこと、移転の周囲に与える影響が少ないことなどを考慮し、判断することが望ましい。
ただし、単体規定のうち、隣接敷地との関係で決まる基準(外壁等で延焼のおそれのある部分の防火措置等)については、敷地内で移転する位置に配慮する等周囲への影響を考慮することが望ましい。
2.用途地域や容積率、建蔽率などの集団規定(法第3章)については、移転先とな
る敷地を適切に選択することによって適合させることが望ましい。しかしながら、用途上既存不適格建築物である建築物が他の地域においては営業の継続が困難である場合等既存建築物(の全部又は一部)そのものの存続が困難となる場合には、特定行政庁が、当該建築物や周囲の状況、これまでの周囲の環境への影響、対象となる規定に係る許可等の実績などを総合的に勘案して判断することも考えられる。
1と2でまとめられ、1については、単体規定、2については、集団規定について書かれています。
1.単体規定
建築物の上部だけを移転(ひきや)するだけなので、上部構造だけをみれば、移転前より悪くならないので、周囲に与える影響は少ないことなどを考慮し、判断することが望ましい。
だだし、単体規定のうち、隣接敷地との関係で決まる基準(外壁・屋根の構造、防火設備等の防火措置等)については、周囲への影響を考慮することが望ましい。
2.集団規定
用途地域、容積率、建蔽率などの集団規定は、適合させることが望ましい。
また、特定行政庁が認める技術的助言であるため、
望ましいと記載していますが、基本的には、適合しなければばらないようになるかと思います。
まとめ
この記事では、
はてな
- 移転とは
- 改正前と改正後の制度の違い
について、解説しました。
移転【法第2条第1項第13号】
建物を解体せずに、そのままの状態で、敷地内および別の敷地に移動させること。
政令で定める範囲で移転する場合は既存不適格適用
下記のいずれかに該当
- 移転が同一敷地内におけるものであること。(既存からの制度)
- 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。(改正により追加)
特定行政庁が認めるものとは
- 単体規定(上部構造)は、移転先の隣接敷地との関係で決まる基準(外壁・屋根の構造、防火設備等)を満たしている。
- 集団規定は、移転先の用途地域規制、容積率、建蔽率等の集団規定の基準を満たしている。
ということです。
また改正後の別敷地の移転の適用については、特定行政庁で運用実績が少ない若しくは全くない可能性もあります。
よって、これを参考に特定行政庁に相談していただけたらと思います。
関連
-

建築工事の種類【法第2条第1項第13号】
一般的に家を建てる場合は、家を建築する、建て替える、増築するといわれます。 また、家をきれいにする場合は、改修するやリフォームするといわれるかたが多いです。 そこで、建築基準法では、工事の種類によって ...
続きを見る
-
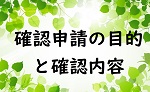
建築確認申請の目的と確認内容とは?【法第6条】
建築物を建築する前には、原則、建築確認申請が必要な工事が法第6条に定められています。 新築はさることながら、防火地域・準防火地域では、1㎡の増築でも確認申請の手続きが必要となります。 そこで、下記の疑 ...
続きを見る
-
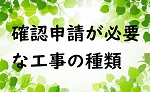
建築確認申請の手続きが必要な工事の種類【法第6条】
建築物の工事をする前に、建築確認申請の手続きが必要です。(法第6条) しかし、建築物の工事の種類といえば、一般的に【新築・増築・リフォーム・改修】などの言い方あります。 よって、小さな増築、リフォーム ...
続きを見る