無窓居室になった際に適用を受ける規定の一つであります、法第35条の3について解説します。
また、令和2年4月1日に改正がありましたので、改正内容も併せて、解説いたします。
また、無窓居室の種類や無窓居室になった際に適用を受けるその他の規定については、下記をご確認ください。
-
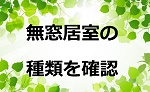
無窓居室の種類を確認しよう【解説】
設計をする際は、極力無窓居室にならないように設計されるはずです。 その際、採光無窓は1/20、換気無窓は1/20、排煙無窓1/50と思っている方は多いと思います。 しかし、それだけではありません! そ ...
続きを見る
-
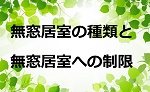
無窓居室の種類と無窓居室への制限
よく無窓居室には、非常用の照明装置の設置をすればいいと安易に考える場合があります。 しかし、無窓居室の種類によって、適用を受ける規制が違います。 そもそも、無窓居室ってどんな状態で、どんな規定がかかる ...
続きを見る
概要
法第第35条の3では、政令で定める下記の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造る必要があります。
政令で定める下記の開口部を有しない居室
政令で定める開口部有しない居室とは
- 採光上有効な開口部の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
- 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上又はその幅75cm及び高さ1.2m以上
居室を区画する主要構造部を耐火構造等
居室を区画する主要構造部(壁・床)は、耐火構造または、不燃材料で造る必要があります。
また、構造の躯体ではない単なる間仕切り壁も、防火・避難上重要な壁となるので、耐火構造等で造る必要があります。
【緩和1】法第35条の3ただし書き
ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途については、耐火構造等の壁は不要となります。
別表第一(い)欄(一)項
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
【緩和2】国土交通省告示第249号
以下の二つの基準を満たす居室は、耐火構造等の壁は不要となります。
【基準1】対象の居室(第1号)
告示第1号の次のイからハまでのいずれかに該当する居室(寝室、宿直室等の就寝の用に供するものを除く。)となります。
居室の種類
イ 床面積が30㎡以内
ロ 避難階の居室で、歩行距離が30m以内
ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、歩行距離が20m以内
歩行距離とは、居室の各部分から屋外(屋外階段)に通ずる出入り口までの距離となります。
【基準2】警報設備の設置(第2号)
令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設置すること。
これら二つの基準に該当すれば、耐火構造等の壁は不要となります。
以上が概要となります。
これからは詳しく解説します。
条文
まずは条文等を確認しましょう。
改正してすぐですので、関連する告示まで掲載します。
参考
法第35条の3
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
令第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)
法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難 上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを 除く。)とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
黄色下線部分が改正され、下記の告示が追加されました。
国土交通省告示第249号(令和2年3月6日)
主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第111条第1項に規定する避難上支障がない居室の基準は、次に掲げるものとする。
一 次のイからハまでのいずれかに該当すること。
- イ 床面積が30㎡以内の居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。以下同じ。)であること。
- ロ 避難階の居室で、当該居室の各部分から当該階における屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下のものであること。
- ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が20m以下のものであること。
二 令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築
物の居室であること。
解説
法第35条の3では、政令で定める下記の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造る必要がありますが、各項目について、解説します。
政令で定める開口部を有しない居室の基準
以下の1、2の開口部のどちらも有しない居室です。
政令で定める開口部有しない居室とは
- 採光上有効な開口部の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
- 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1mル以上又はその幅75cm及び高さ1.2m以上
上記1.2どちらの開口部もない居室が規定を受けることになります。
よって、どちらかの開口部があれば法第35条の3の規定は適用されません。
採光上有効な開口部
1/20以上の開口部(令第111条第1項第1号)の面積の計算方法は、令第20条と同様の計算方法となります。
詳しくは、下記をご確認ください。
-

有効採光面積(採光補正係数)の算定方法【解説】令第19条
法第28条で居室に必要な採光上有効な開口部の面積が定められています。 その開口の面積は、開口の面積×採光補正係数で算出します。 また、開口部から居室内に入る光の具合は、開口部ごとで違います。 よって、 ...
続きを見る
また、令第111条第2項の規定のふすま・・・の規定は、法第28条第4項の採光・換気の2室1室の規定と同様の扱いとなります。
耐火構造が求められる主要構造部
耐火構造等が求められる主要構造部ですが、その居室を構成する壁(間仕切り壁を含む)・床となります。
また、構造の躯体ではない単なる間仕切り壁も、防火・避難上重要な壁となるので、耐火構造等で造る必要があります。
主要構造部とは
主要構造部とは、防火・避難上重要なため耐火・防火性能が必要される部材のことです。
主要構造部は法第2条第5号に記載しています。
よって、耐力壁でもないただのLGSにボード貼った間仕切り壁でも、防火避難上主要な間仕切り壁となるので、主要構造部となります。
防火上主要な間仕切り壁の規定についても、同様です。
-
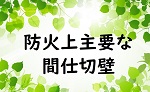
【114条区画】防火上主要な間仕切壁の規定(令第114条第2項)
通称【114条区画】施行令第114条第2項の防火上主要な間仕切壁について記事を書いています。 最近は木造建築物の規制緩和や、木材利用促進やそれに合わせて、小規模福祉施設、小規模の宿泊施設の増加していま ...
続きを見る
また、主要構造部と構造体力上主要な部分は、文字として見ると似ていますが、違いますのでご注意ください。
耐火構造または不燃材料とする範囲
天井裏もしくは小屋裏まで耐火構造等する必要があります。
過去のパブコメで以下の質疑応答があります。
意見
無窓居室を構成する天井は主要構造部ではないため、〝居室を区画する…"を満たすためには、間仕切壁は、防火区画のように天井裏もしくは小屋裏まで達せしめなければならないか。
国交省の考え方
貴見の通り。
天井までなら比較的容易にですが、床、屋根までするとなると大変です。
耐火構造等の部分を貫通する配管等の貫通処理
目的は、防火上主要な間仕切り壁と概ね同様ですので、防火上主要な間仕切り壁と同様の区画貫通処理を求められる場合があります。
しかし、特定行政庁等によって、取扱いが違います
防火上主要な間仕切り壁の区画処理は、令第114条‿5項→第112条第19項に記載されています。
参考
令第114条第5項
第112条第19項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第20項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。(以下、略)
令第112条第19項
給水管、配電管その他の管が第1項、第3項から第5項まで若しくは第17項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第6項若しくは第9項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第10項本文若しくは第15項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
区画する壁の仕様は準耐火構造ではだめ
区画で求められる壁の仕様は、‿耐火構造または不燃材料となっています。
不燃材料がOKであるなら、準耐火構造でいいのではないかと思いませんか。
また、他の区画等の壁は、準耐火構造からとなっています。
しかし、法改正のパブコメの質疑応答で、耐火項構造または不燃材でつくる必要があると国交省が回答しています。
ただし書き・告示で区画免除
法別表第1(1)項(法第35条の3ただし書き)
法第35条の3の条文に
参考
ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
と記載されています。
別表第一(い)欄(一)項の用途は下記の建築物です。
- 劇場、映画館、演芸場
- 観覧場
- 公会堂
- 集会場
上記の建築物については、耐火構造等の壁は不要となりますが、小規模のものを除いて耐火建築物等にする必要があります。
避難上支障がない居室(国土交通省告示第249号)令和2年4月1日施行
令第111条が2020年4月1日に改正しました。
内容は、避難階または避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合するものは除く。とされました。
以下で、詳細をご確認ください。
二つの基準を満たして緩和
これら二つの基準に該当すれば、耐火構造等の区画は不要です。
【基準1】対象の居室(第1号)
告示第1号の次のイからハまでのいずれかに該当する居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。以下同じ。)となります。
居室の種類
イ 床面積が30㎡以内
ロ 避難階の居室で、歩行距離が30m以内
ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、歩行距離が20m以内
歩行距離は、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口までの距離です。
簡単にいいますと、居室の各部分から屋外に通ずる出入り口までの距離となります。
【基準2】警報設備の設置(第2号)
令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設置すること。
参考
令第110条の5
法第27条第1項第1号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
また、今回の改正は、法第35条の3の規制の合理化であり、その他の無窓居室の合理化ではないため、従来通りの対策が必要となりますのでご注意ください。
まとめ
以上、法第35条の3の解説をしました。
この記事は、条文等を載せているため、少し長くなりましたので最後にまとめます。
法第35条の3→令第111条→告示第249号
政令で定める下記の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造る必要があります。
政令で定める開口部有しない居室とは
- 採光上有効な開口部の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
- 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上又はその幅75cm及び高さ1.2m以上
主要構造部ですが、その居室を構成する壁・床(屋根)を耐火構造または、不燃材料で造る必要があります。
また、構造の躯体でもない、単なる間仕切り壁であっても、防火・避難上重要な壁となるので、耐火構造等で造る必要があります。
しかし、法第35条の3のただし書き、または、告示にの条件を満たす居室は、区画が不要となります。
【緩和1】法第35条の3ただし書き
政令で定める開口部を有しない居室でも、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途および告示に記載されている居室については、緩和の規定があります。
- 劇場、映画館、演芸場
- 観覧場
- 公会堂
- 集会場
【緩和2】国土交通省告示第249号(令和2年4月改正)
以下の二つの基準を満たす居室は、耐火構造等の壁は不要となります。
基準1】対象の居室(第1号)
告示第1号の次のイからハまでのいずれかに該当する居室(寝室、宿直室等の就寝の用に供するものを除く。)となります。
居室の種類
イ 床面積が30㎡以内
ロ 避難階の居室で、歩行距離が30m以内
ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、歩行距離が20m以内
居室の各部分から屋外(屋外階段)に通ずる出入り口までの距離となります。
【基準2】警報設備の設置(第2号)
令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設置すること。
これら二つの基準に該当すれば、耐火構造等の壁は不要となります。
以上が、法第35条の3の解説となります。
この記事をみていただきありがとうございます。
関連
-
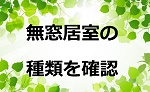
無窓居室の種類を確認しよう【解説】
設計をする際は、極力無窓居室にならないように設計されるはずです。 その際、採光無窓は1/20、換気無窓は1/20、排煙無窓1/50と思っている方は多いと思います。 しかし、それだけではありません! そ ...
続きを見る
-
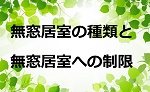
無窓居室の種類と無窓居室への制限
よく無窓居室には、非常用の照明装置の設置をすればいいと安易に考える場合があります。 しかし、無窓居室の種類によって、適用を受ける規制が違います。 そもそも、無窓居室ってどんな状態で、どんな規定がかかる ...
続きを見る
-

ビニールハウスは建築物に該当します!建築物に該当しない基準を確認しよう
ビニールハウスをつくりたい! しかし、建てるために相談したら、ビニールハウスを建築物に該当するって言われたけど本当?? ビニールハウスなのに、建築物に該当するのは困る!! 私も仕事で設計者や建築主と相 ...
続きを見る
-

ビニールハウスは建築物に該当します!建築物に該当しない基準を確認しよう
ビニールハウスをつくりたい! しかし、建てるために相談したら、ビニールハウスを建築物に該当するって言われたけど本当?? ビニールハウスなのに、建築物に該当するのは困る!! 私も仕事で設計者や建築主と相 ...
続きを見る