一般的に家を建てる場合は、家を建築する、建て替える、増築するといわれます。
また、家をきれいにする場合は、改修するやリフォームするといわれるかたが多いです。
そこで、建築基準法では、工事の種類によって規制であったり、工事の種類によって、建築確認申請が必要となります。
そこで、この記事では、
はてな
建築基準法で定められている、建築工事の種類とは?
について、解説します。
また判断に迷う場合は、この記事を参考に特定行政庁にご確認ください。
建築工事の種類
建築基準法では、建築工事の種類として下記のとおり定められています。
建築【法第2条第1項第13号】
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。
大規模の修繕、大規模の模様替【法第2条第1項第14号・第15号】
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
改修・リフォーム
建築基準法では、定められていません。
一般の方を含め、建物の一部をきれいにするなどの工事について、改修・リフォームと呼びます。
解説
建築の定義【法第2条第1項第13号】
建築とは、法第2条第1項第13号に定義されています。
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転するこという。
新築の定義
考え方として、下記の二つがあります。
- 建築物がない敷地(更地)に、新しく建築物を建てる。
- 既存の建物がある敷地に、別棟で建築物を建てる。建築物ごとで考えると新築となります。
増築の定義
同じく考え方として、下記の二つがあります。
- 既存の建築物を増築する。
- 既存の建築物がある敷地に、別棟で建築物を建てる。敷地で考えると増築となります。
防火地域・準防火地域の増築は0㎡からでも建築確認申請の手続きが必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
改築の定義
すでにある建築物の全部もしくは一部を除却または滅失した後に、引き続き以前の用途・規模、構造が著しく異ならない建築物を建てることです。
以前のものと著しく異なる場合は、新築または増築となります。
また一旦除却または滅失し、一定期間経過すると、新築または増築となります。
改築で確認申請を提出する場合は、特定行政庁または民間確認検査機関にご相談ください。
参考
かなり前にはなりますが、照会・回答がありますので、記載しておきます。
改築の定義(昭28.11.17住指発1400)国家消防本部総務課長宛
(照会)改築の定義をされたい。
(回答)改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときあ、新築または増築となる。なお、使用材料の新旧は問わない。
移転の定義
すでにある建築物を解体することなく、そのままの状態で移動させることです。
通称、曳家(ひきや)とも言います。
既存の建築物を一度解体し、別の場所で再度組み立てる場合は、新築になります。
移転についてこちらにまとめましたのでご確認ください。
改修・リフォーム
また、そのほかに改修・リフォームと言われますが、特に法律上、定義づけがされていません。
単純に上記の建築に含まれない、下記のような工事をいいます。
- クロス・床を張り替える
- キッチンなどの設備を取り換える
- 簡易な壁を作る、壊す
- 外壁にペンキを塗る
大規模の修繕、大規模の模様替の定義【法第2条第1項第14号・15号】
法第2条第1項第14号に大規模の修繕、第15号に大規模の模様替が定義づけされています。
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
大規模
修繕や模様替を行う範囲が、主要構造部の一種以上について行う過半に至る場合のことです。
修繕
既存のものと概ね同じ位置に、概ね同じ形状寸法で、概ね同じ材料を用いてつくりかえ、性能や品質を回復する工事のことをです。
模様替
概ね同じ位置でも、異なる材料や仕様も用いて造り替え、性能や品質を回復する工事のことです。
詳しくはこちらの記事で【大規模の修繕・模様替】についてまとめていますので、ご確認ください。
まとめ
この記事では、
はてな
建築基準法で定められている、建築行為の種類とは?
について、解説しましたので、最後にまとめます。
建築【法第2条第1項第13号】
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。
大規模の修繕、大規模の模様替【法第2条第1項第14号・第15号】
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
改修・リフォーム
建築基準法では、定められていません。
以上、最後にまとめました。
特定行政庁によって、扱いが違うところがあるので、これを参考に確認していただけたらと思います。
関連
-
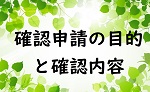
建築確認申請の目的と確認内容とは?【法第6条】
建築物を建築する前には、原則、建築確認申請が必要な工事が法第6条に定められています。 新築はさることながら、防火地域・準防火地域では、1㎡の増築でも確認申請の手続きが必要となります。 そこで、下記の疑 ...
続きを見る
-
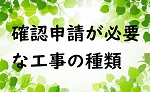
建築確認申請の手続きが必要な工事の種類【法第6条】
建築物の工事をする前に、建築確認申請の手続きが必要です。(法第6条) しかし、建築物の工事の種類といえば、一般的に【新築・増築・リフォーム・改修】などの言い方あります。 よって、小さな増築、リフォーム ...
続きを見る
-

移転の取扱いが変わりました(平成27年改正)
建築物の移転といえば、プレハブの事務所や倉庫をレッカーなどで動かすことや、(通称)仮設便所を動かすなどが想像されます。 また移転について、平成27年(2015)制度の改正がありました。 そこで、この記 ...
続きを見る
-
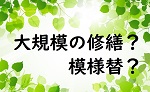
大規模の修繕および大規模の模様替とはどんな工事?
建築物は建築後、月日の経過とともに、傷んできます。そのときに「修繕等」を行うかと思います。 そんなとき、特定行政庁や民間確認検査機関に相談すると、その工事は、大規模の修繕・大規模の模様替に該当するので ...
続きを見る
